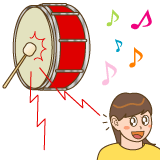音の伝達通路は2系統ある
音が聞こえるメカニズムからの続きです。
中耳から伝わってきた空気の振動は、
内耳の「蝸牛」で電気信号に変換されます。
蝸牛は名前の通りカタツムリの殻のような形をしています。
内部は2階建てになっていて、
上段は「前庭階」
下段は「鼓室階」といいます。
上段と下段の間に「蝸牛管」という膜でできた管があります。
前庭階と鼓室階には外リンパが、蝸牛管の中には内リンパが
それぞれ入っています。
蝸牛管の上部には「ライスネル膜」下部には「基底板」という膜があります。
基底板の上には振動を感じる感覚細胞があり、
蝸牛神経(聴神経)とつながっています。
耳小骨(アブミ骨)が伝えた空気の振動は、前庭窓から蝸牛内部へ進入します。
すると前庭階を満たす外リンパが波打ち、基底板をゆらします。
音の高低によって揺らす場所が変わり、
高い音は蝸牛管の手前の基底板を揺らし、低い音は奥の基底板を揺らします。
基底板の揺れを感覚細胞が受け取り電気信号に変換しています。
この電気信号は蝸牛神経を通って、大脳の聴覚野に伝わっていき、
大脳の聴覚野によって、はじめて言葉や音楽などの「音」として
認識されます。
聞こえのメカニズムは、
音を伝える外耳から中耳までの「伝音系」と
音を感じる内耳・聴神経・脳までの「感音系」でなりたっています。
聴力検査で2種類あるのはこのためです。
これら2つの伝導路でどこかトラブルが起こると
耳鳴りや難聴がおきてしまいます。
関連記事

からだの調子はお天道様が決める?
まだ梅雨明けしていませんが、 台風が来たり、暑くなったりと 天気や気温の変動が激しくてなかなかシンドイ日が続きますね この時期の気候は、 めまいだったり、ふらついたり、耳鳴りがひどくなったりし[…]

めまいとは?
普段、動いているか止まっているかに関わりなく、 周囲と自分の関係をつねに感じ取っています。 空間見当識(くうかんけんとうしき)と呼ぶのですが、 これがつねに働いているからこそ、 姿勢や動作を安定することができます。 めま[…]

気象病?天気病?からだの調子が変なんです・・・
天気病もしくは、気象病と言われるものがあります。 昔、おばあちゃんが雨の前の日は 膝が痛くなってね。というようなものを 想像してもらえるとよいです。 最近はもっと詳しく定義づけられようになっています。 &n[…]

のぼせの原因ってなんだろう?
めまいのふらふら・ゆらゆら・回る感じ とは別の「かーっとおでこのあたりが熱くなる」 ことや「ホットフラッシュ」のように 急に汗が出る状態もしばしばあります。 この時の原因は何か? 鼻の状態が原因となります。[…]

めまいの種類・・・回転性めまい(ぐるぐるめまい)
回転性めまい(ぐるぐるめまい) 症状として ・周囲のものがグルグル回る ・周囲のものが一定方向に流れていくように見える ・自分の体がぐるぐる回るように感じる ・カラダがぐらりと回転し倒れる これらは、 内耳障害によっても[…]