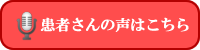めまいに鍼灸治療が良い理由
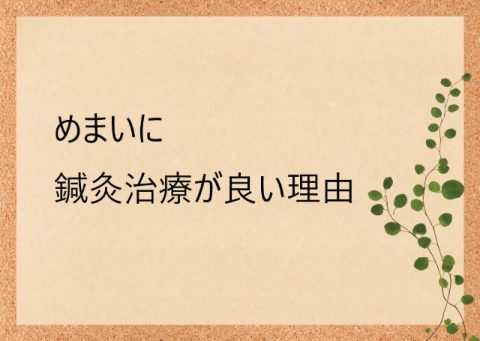
今回はめまいに悩むあなたに
めまいはどうやって起きるのか
たけちはり灸院では
どんな治療をしているかを
紹介していきますね。
その前にひとつだけ注意事項があります。
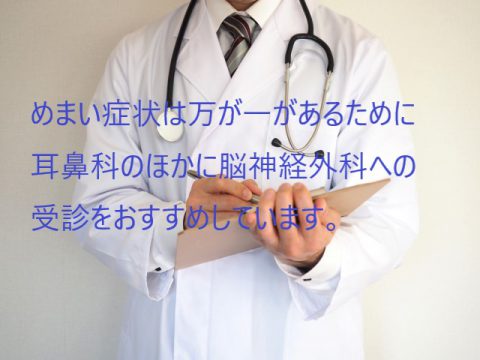
それでは、4つに分けて説明していきますね。
①回転性めまいと非回転性めまい
②平衡感覚とめまい
③たけちはり灸院での鍼灸治療
④最後に
①回転性めまいと非回転性めまい
めまいには
回転性めまいと
非回転性めまいがあります。
回転性めまいとは
まわる
ぐらぐらする
頭とからだがわかれる、などの
症状が起こってきます。
非回転性めまいは
揺れる、頭が落ち着かない
という症状のでる動揺性めまいや
地に足がつかない
宙に浮いた感じ
足に力が入らない
床がスポンジのようで沈む
という症状の出る浮動性めまいがあります。
めまいを引き起こしやすいのは
狭い空間にいるとき
横の状態から起き上がるとき
上の物や、かがむ、方向転換するときなどです。
②平衡感覚とめまい
わたしたちのからだは
耳と目、足の3つのセンサーが
はたらくことで平衡感覚を保つことが出来ます。
内耳にある
三半規管(たて、よこなどの動きを感じる部分)
視覚(目から入る情報)
運動感覚(足で立っているときの情報)です。
ところがこれらの情報が一致していないと
脳内の情報が混乱してめまいが生じます。
③たけちはり灸院での鍼灸治療
たけちはり灸院では
3つのポイントに注目します。
内耳のツボ、目のツボ
足の過度な緊張を取ること、です。
内耳には三半規管があり
ここがトラブルを受けていると
めまいの他に吐き気や動悸、息切れなどが
起きてきます。そのため大事なポイントです。
光がまぶしく感じたり、ピントが合わない
というめまいのある方も多いです。
そのため、眉間やこめかみにある
目のツボを刺激をすることも必要です。
足腰がしっかりしない、ふらつくなどの
症状がある方もおられます。
そのためふらつかないように
足の筋肉が緊張しすぎて
パンパンになっていることがあります。
足の緊張をほぐすための治療をします。
さらに、めまいで緊張したからだをほぐし
消耗した体力を回復させるために
鍼灸治療を行います。
めまいのある方には
首肩、背中のコリが強い人が多いです。
からだのコリをとることで
めまい以外の身体的なストレスも減ります。
また、めまいは体力を大きく消耗します。
そのため内臓の機能が落ちやすくなります。
内臓のはたらきが落ちるとつかれやすくなり、
めまいを感じやすくなります。
おなかのツボに刺激を加えることで
体力を回復させます。
④最後に
今回は平衡感覚、すなわち内耳と目、
足のトラブルでおこるめまいに
着目してどんな治療をしているか
ご紹介しました。
たけちはり灸院では
あなたがいつから、
どのようなめまいが起きて
どんなことで困っているのか
しっかりお話を聞きます。
あなたの症状に合わせて
不安や疑問に思うことについて
ひとつひとつ取り除いていきます。
めまいでお悩みでしたら、気軽にお電話くださいね!
ご予約
052-753-7716
関連記事

耳鳴りのセルフケア ・・・ 耳鳴りを鍼灸治療で治すために知っておいて欲しいこと
大なり小なり耳鳴りに悩まされている人はとてもたくさんいます。 名古屋市名東区にあるたけちはり灸院は耳鳴りでお困りの方に 鍼灸治療をさせていただいています。 耳鳴りを鍼灸治療で治すために知ってお[…]

耳鳴りは探さないことも大切なんです。
耳鳴りの患者さんから 「耳鳴りが気になって眠れない」 「耳鳴りがどんどん大きくなってイライラする」 「耳鳴りの音の種類が変わってきた」 など、日々耳鳴りの変化について教えていただきます。 鳴っ[…]

異常ないっていうけど、○○は大切な治療ポイントですよ
耳のトラブルが起こっているかたの 傾向として多いのが、鼻のトラブルを お持ちのかたがいます。 自覚のないかたもたくさんいます。 もちろん副鼻腔炎や後鼻漏(こうびろう)、 花粉症など鼻の炎症も耳に悪さをします[…]

知っておいて損はないオージオグラムの見方
聴力のトラブルがあって耳鼻科にかかると聴力検査というものを行います。 防音室にはいってヘッドホンをして「ピー」とか「ブー」とかの 音が聞こえたらボタンを押すという検査です。 健康診断などではにぎやかなところ[…]

難聴で当院の鍼灸治療を受けた方のお声 ・・・ 難聴を鍼灸治療で治すために知っておいて欲しいこと
突発性難聴でお困りの方はとてもたくさんいます。 名古屋市名東区にあるたけちはり灸院は突発性難聴でお困りの方に 鍼灸治療をさせていただいています。 突発性難聴を鍼灸治療で治すために知っておいて欲しいことを書い[…]